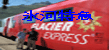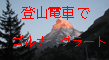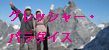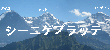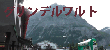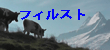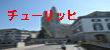NOBURINのスイス紀行 2012/8/14
グリンデルワルトからルツェルンへ列車の旅
グリンデルワルトからルツェルンやチューリッヒに行くには、インターラーケンから首都ベルン経由の特急列車に乗れば時間的に早く着く。私たちは急ぐ旅ではない。のんびりと急行列車で景勝ルート、インターラーケン~ルツェルンのコースを選んで車窓を楽しむことにした。 グリンデルワルト8:19発、インターラーケン9:04発、ルツェルン11:04着というスケジュールで行く。ルツェルンで午後四時まで観光も出来る。そして同日ルツェルン16:10発でチューリッヒに16:56に到着したのでした。
ルツェルン

町の中央を流れるロイス川、そこに斜めにかかるカペル橋
NOBURIN&緑子 は、8月14日(火)いよいよアルプスを離れ、グリンデルワルトからインターラーケンを経由してルツェルンという古い町に立ち寄りました。ここもかつて、NOBURINが来たことのある町でしたが、あまり記憶に残っていません。今回はしっかりと見ておこうと思います。もう来ることはないだろうから。 NOBURINの薄い記憶にも屋根付きのカペル橋を渡ったことは覚えています。ルツェルンといえばこの橋がシンボルです。橋の完成は中世にさかのぼり、その役割は隣接の湖から攻めてくる敵をここで食い止める城壁だったのだそうです。左に見える八角形の塔は見張り台だったり捕虜の拷問部屋だったりしたという。今は明るい中世の旧市街だが、歴史をたどると何か目前に寒気をもよおすものがありました。

カペル橋の外(左)と屋根の下(橋の上)

橋の梁には古い絵がたくさん掲げられています。

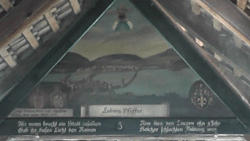
そもそも、カペルというのは教会(チャペル)と言うこと。で、カペル橋とは、教会の橋。つまり、カペル橋の延長線上にイエズス教会、フランシスコ教会があり、反対方向の延長線にはザンクト・ペータース教会とホーフ教会があります。城壁の橋であり、教会を結ぶ橋でもあるのです。 そこで、カペル橋の延長線をたどって教会を訪れることにしました。
フランシスコ教会・ホーフ教会
私たちはロイス川を挟んでフランシスコ教会と片方のホーフ教会を訪ねました。カペル橋のたもとの四つの教会ともカトリックです。宗教改革の当時 ルツェルンは、改革に最も強く抵抗した町なのだそうです。スイスの宗教改革では、かたやチューリッヒ、かたやルツェルンだったのでしょう。

フランシスコ教会の玄関とそこにある聖母子像

フランシスコ教会の玄関には聖母子像がたたずみ、会堂の中もプロテスタントの教会とは趣が違います。
.jpg)
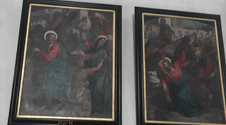
会堂の正面には飾りの付いた祭壇があり、壁面にはキリストの生涯を描いた聖画がずらりと掲げてあります。
次に、隣のイエズス教会と向こう岸のザンクト・ペータース教会は素通りして、ホーフ教会へ向かいました。
.jpg)

ここにも祭壇があり、聖画が掲げられています。祭壇は何を意味するのでしょう。NOBURINにはよく分からないけれど、聖画は貴重な芸術品であると同時に、神の国やキリストの救いを表現する視覚教材でもあるのです。キリスト教に限らず、いずれの宗教画は教材として用いられているようです。NOBURINが、先日菰野の正眼寺で見せてもらった秘宝 釈迦涅槃図もそうしたもののように思えます。


会堂に隣接してお墓と納骨堂がありました。グリンデルワルトやツェルマットの教会でも会堂のすぐわきにお墓があります。イギリスのコッツウォールズの教会でもそうでした(そこではむしろ庭全体がお墓という感じ!)。誰彼となく訪れるお墓、足音聞こえて来て日曜日ごとに讃美歌の聞こえるお墓、そんな教会はいままで日本では見たことがありません。
町歩き
カペル橋を渡るとルツェルンの旧市街です。とても明るく活気に溢れています。古い町にはどこにも昔からの噴水があるようです。ここでもおもしろい噴水の泉を見ました。クールの町でもそうでした。おそらく単なる町の飾りではなく、各家庭に水道のなかった時代には町の人たちの生活の場だったのでしょう。いわゆる井戸端会議もあったのでしょう。フレスコ画と花で飾られた美しい家々も目をひきます。


そろそろお昼も近づいてきました。今日はお弁当の用意もしていないのでレストランを利用することにしました。私たちは、お店でメニューを見て注文するのは外国では苦手なので、前もって決めておきました。ピザ一皿とサラダ一皿。それにNOBURINは一杯のビール、緑子さんは水。これは正解でした。ウェイトレスは、私たちのオーダーをすぐに理解してくれてあまり時間もとらずに注文の品を持って来てくれました。その量も二人でいただくのに適量。でも、そのウェイトレスがこちらをちらちら見ているようでもありました。何せ、同じくピザを食べていた隣の席の数人の若い女の子達はそれぞれ一皿をぺろりと食べていたのでした。


ひん死のライオン
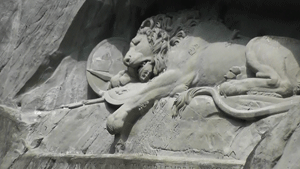

ホーフ教会から10分ほど歩くとライオン記念碑に行きます。このライオンは猛々しいライオンとは意に反して息絶え絶えのひん死のライオンです。横腹には槍が刺さっています。これはスイスが今日のように華やかな時代とは異なり、およそ200年ほどさかのぼり若者は隣国の傭兵として出稼ぎに行きました。1792年(日本では江戸時代 寛政の改革 の頃かな?)フランス革命の際、民衆からルイ16世とその后マリー・アントワネットを守ろうとして命を落とした786名の傭兵を悼んで作られたものだそうです。ここにも貧しかった頃のスイスの歴史を垣間見るような気がしました。
スイスホルンで アメイジング・グレイス

旧市街よりカペル橋とは反対のシャプロイヤー橋を渡ってフランシスコ教会へ向かうとき、突然スイスホルンを抱えたおじさんが路上に出てきて通りに向かって吹奏を始めました。ホルンの音を確かめるためか町を訪れた人たちに聞かせるためか分からないのですが、とにかく私たちは立ち止まりました。耳を傾けるとなんだか聞き覚えのある曲です。アメージング・グレイスです。教会の讃美歌に取り上げられているあの曲だったのです。NOBURINのビデオで紹介したように曲のはじめから終わりまで聞いていました。吹奏が終わったとき歓声と拍手を送ったのは私たちだけでした けど・・・・。 スイスホルンに出会ったのは、シーニゲプラッテに続いて2度目のことでした。
NOBURIN作成のビデオをYouTubeでご覧下さい

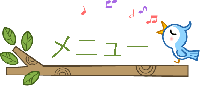
下の表にある各項目をクリックすると、それぞれのページをご覧頂けます。
電車の旅

グリンデルワルト駅を8時19分発

インターラーケン東駅着 8:54着
同 9:04発
.jpg)
ブリエンツ湖

途中停車駅で
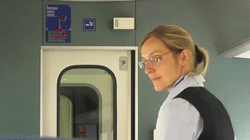
女性車掌

サルネルゼー

ギスヴィル

サーンでは自衛隊いえスイス軍の兵士だ

ルツェルン駅 11:04着