

八郷のまちづくりは平成13年6月頃、有志8名で将来の八郷について語り合ったのが始まりでした。毎月2〜3回の議論を重ね平成14年1月、八郷地区における地域課題を以下のようにまとめ、地域のみなさまや地域団体の代表者に趣旨をご案内して協力を求めることにしました。
平成14年4月からは「八郷まちづくり委員会」として出発し、地域の活動団体の一つとして順次、課題への取り組みを進めていくことになりました.地域のみなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。
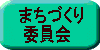 topへ topへ |
課題1.「高齢者問題」について
急速な高齢化社会の到来を受けて多くの問題が山積しているが、社会の一員として、その豊かな経験と知識を活かしつつ、何の不安もなく、健やかに人生の終鳶を迎えられる事が万民の望むところではないでしょうか。高齢者の方々が抱かえる問題点を明らかにし、地域としての対応策を考えると共に、各人が持てる力を精いっぱい発揮して、いきいきとしたシルバーエイジを過ごしていただくための事柄を中心に取り組みを進めていきたい。
具体的には、
1 人材バンク制度の立ち上げと活用。
取得免許、特技、経験、趣味等を登録してもらい、活用できる場に向けて適宜発信をする。
2 小・中学校の総合的学習時間への参加。
豊かな人生経験をもとに、総合的学習の本旨である「人としての生き方」や特技、趣味等を活かしたメニューを整え、学校の要望 に応える、或いは提案を試みる。
3 居宅のバリアフリー化の促進。
居宅内での転倒事故防止や在宅介護を円滑にするための住宅改修について、制度(助成金の有無、額等)・仕組みの広報、地区社会福祉協議会や民生委員との協働や研修の実施。
4 高齢者の意識調査の実施。
アンケート調査により現状を把握し、今後の取り組みに活用する。
課題2.「女性問題」について
近年、女性の人権に関わる問題が頻発しているが、女性問題についてはややもするとタブー視されたり、家庭内の問題とする風潮が強かったが、人権意識の高揚と共に、法整備や関係諸団体の対応も遅まきながら充実してきたことを受け、あらゆる機会を通して広報、啓発の運動を展開する。
具体的には、
1 DV、セクハラ、ストーカー行為の未然防止。
地域社会のなかで、これらの問題のタブー視をなくし、人権問題として捉える必要性を訴える。チうシの作成・配布、研修会等の 機会を設け啓発活動の取り組みを進める。
2 女性の意識調査の実施。(まちづくりへの参加意識)
アンケート調査により現状を把握し、今後の取り組みに活用する。
課題3.「子どもの問題」について
子どもを取り巻く環境は、一般社会と同様に複雑でさまざまな姿を示しながら変化をしています。学校におけるいじめ、不登校、校内暴力等の問題や、家庭の中での育児疲れや育児不安等から生じる子どもの虐待問題まで数多い問題を抱かえていますが、今回は、地域として関わることのできる「学校週5日制」による地域の受け皿、総合的学習の実践による地域の関わりについて考えてみたい。
具体的には、
1 総合的学習の時間(授業)への参画。
特技、趣味等を活かしたメニューを整え、人的手当をし学校の要望に応える。(高齢者問題②と共通あり)
2 学校週5日制による地域の受け皿づくり。
地域や家庭における生活の大切さを社会体験、自然体験、人的交流を通して学ぶ機会の提供。
こども会活動やスポーツ少年団活動の活発化。また、子どもに関わる諸団体(PTA、こども育成者会、少年団育成者等)や学校 との意見交換会の実施。
3 子どもの意識調査の実施。
アンケート調査により現状を把握し、今後の取り組みに活用する。
課題4.「環境問題」について
環境問題は複雑多岐にわたるが、今、直面しているゴミの問題。分別収集、減量化、不法投棄等解決すべきことは多いが、とりわけ八郷地区では道路沿いや河川敷への不法投棄(ポイ捨て)が後を絶たず深刻な問題となっている。
また、分別についてもまだまだ守られていないのが現状であり、これらの事柄を踏まえ実体験を通して環境美化の啓発を進めていく。
具体的には、
1 「まち一斉ゴミ拾いの日」の設定と実施。
子どもからお年寄りまで、地区民総出(4000人規模)で八郷地区内の清掃活動を実施する。実体験をもって現状をよく知り、汗をかきながら美しい八郷を残すことを考える。
ボランティア精神の育成とボランティア手帳の製作。
2 「花いっぱいのまちづくり計画」の実施。
花があり、潤いのある美しいまちづくりを目指す。そのための必要な組織づくり、場所の選択・確保、予算手当等を考えてみたい。
課題5.「健康づくり」について
地域における「健康づくり」の取組みに目をむけてみると、あまり必要でない今一番健康な年齢層を中心に進められています。地域には幼児から高齢者まで、実に幅広い年齢の方が住んでいます。それぞれの年齢や体力など、また、健康事情に合わせた取組みが必要と考えます。
具体的な取組みとしては今回、提案を見合わせています。
課題6.「危機管理」について
火災(山火事を含む)、水災(川、ダムの氾濫、決壊等)、地震災害等のさまざまな災害が考えられますが、本年度、東海沖地震の震源想定地の見直しや、それに伴う被害想定も大幅に見直しされており、今回は特に地震について考えてみたい。
具体的には、
1 「危機管理意識」の啓発活動の必要性を訴える。
震災から生命や財産を守るために今、何が必要か、何をすべきかを考え、また、家屋の耐震診断や非常持出し品の備え等、資料の 配布もしながら啓発活動を通して地区住民の危機管理に対する意識の高揚を図っていく。
2 各町の自主防災隊体制の現状把握と見直し、消防分団との連携。
現在、各町の自主防災隊の体制は殆ど形骸化していて、災害発生時にはきちっと機能しないのではないだろうか。専門家の指導のもと、実情に合わせたマニュアルを作成し、各種の訓練においては八郷消防分団との連携のもと計画的に行う必要がある。また、災害ボランティアの養成も急務。
課題7.「組織のあり方の見直し」について
まちづくりは地域全体に関わる問題であり、地域をあげて取り組まなければ到底なし得ない事柄ばかりです。八郷地区の課題、問題に取り組んでいくうえで、自治会をはじめ各種団体、或いは地域の役割を担っている方々との連携は必要です。課題、問題の認識を共有することはもちろんのこと、意見交換や協働して関わることは大切なことだと思います。例年、事業の大半が従来の踏襲をしているだけでは…?と指摘される現状において、場合によっては組織の見直し、人心一新も必要になってくるのではないでしょうか。
具体的には、
1 懇談会の実施が必要。
全ての団体や役割の参加する懇談会(交流会)を実施し、八郷地区の現状を確認すると共に、今後の取り組みがそれぞれにとって有効且つ、効率良く(費用、労力等)実行できる工夫が必要。
2 「八郷まちづくり」スタッフについて
従来の「八郷地区地域社会づくり推進委員会」の充て職的な委員の選出を廃止し、その仕組みと共に顔ぶれが大きく変わりました。名称も「八郷まちづくり委員会」とし、住民のみなさんに親しんでご参加いただけるよう工夫をする。
3 平成14年度≪八郷まちづくり委員会委員≫
石原 久美子(あかつき台1丁目)
今川 晃(四日市大学教授)
大島 保(平津新町)
岡野 丘(平津新町)
河西 博行(市民センター館長)
北村 実(連合自治会代表)
久保田領一郎(あかつき台1丁目)
小林 昭郎(伊坂町)
佐藤 久美子(あかつき台6丁目)
長谷川 裕之(千代田町)
松田 和之(あかつき台6丁目)
松田 幸郎(あかつき台2丁目)
村上 悦夫(連合自治会長)
村上 伸子(山分町)
毛利 良一(山分町)
吉田 正成(広永町)