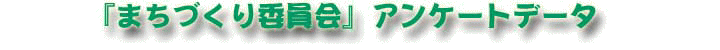
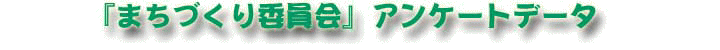
| 高齢者の意識調査 |
| 女性の意識調査 |
| 子どもたちの意識調査 |
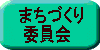 topへ topへ |
| 対象者の年齢 | 対象人数(人) | 回答数(人) | 回収率(%) |
| 60才以上の女性 | 1,467 | 1,091 | 74.4 |
| 60才以上の男性 | 1,333 | 1,007 | 75.5 |
赤字は質問事項です
あなたの家族構成は
核家族化が進んでいるなかで、ひとり暮らしの方が127人(男28人、女99人)います。これは子供がいないひとり暮らしの方41人と、市内外に子供がいる86人の方の人数です。多いか少ないかは問題ではありませんが、ご高齢だけに病気や怪我で寝込んだ場合の心配が考えられます。
また、こうした核家族化の結果が今、子育て中の女性にとって「子育ての不安や悩み」となり、「子育ての支援」を大きく求める要因になっていると思われます。
あなたの趣味、特技、取得免許や興味を持っている事柄について
それぞれの方がいくつもの趣味や特技や免許を持っておられます。それらが現在も活かされている場合は良いのですが、活かしたいが場所がないと思われている方が大半ではないでしょうか。たいへん惜しい気がします。
旅行やカラオケ、ゴルフ等の趣味と同じように、地域のサークル活動やボランティア活動への興味を深めることで活かすことができるならば、ご自身の生き甲斐につながることになるのではないでしょうか。
学校の総合学習の時間に地域先生として関わる意志は
男性13.5% 女性10.0%
地域社会への貢献意欲を尋ねています。これは講師となって子どもたちに様々なことを教えたいか、また、高齢者が自分の経験や知識を伝承するなかで、子どもたちとの関わりの意志を問いかけていますが、男女合わせて約1割の方が意欲ありと答えています。
また、同時に地域の教育力の活用方法を模索しているわけですが、その割合が1割とは少し淋しい結果です。「わたしの経験なんて」という謙遜もおありなのでしょうが、長い歳月を経てきた人の言葉は身近な事柄についての話しでも、子どもたちにとっては 立派な教材になります。趣味や学習に参加して「学ぶ側」に回る高齢者の比率と同じくらいいると良いと思います。
参加意志の比率は、60才代の若い高齢者だけをとらえてみても同様で、また旧町、団地の比較でも同様の傾向が伺えます。
地域にボランティア組織があれば利用するか
男性26.7% 女性34.4%
日常生活をするなかで、何らかの他人の手助けが必要と思っている高齢者が3割、食事という生きていくための最低限必要な事柄にさえ手助けを求めている高齢者が1割います。また、逆に自立し、他人を支援する側に回る高齢者が3割(地域でサークル活動や同好会に入っている2割と、地域で何かの役割を持っている1割)います。
一見、支援される側は楽そうですが、生きがいを持って暮らせるのは、支援する側に回る高齢者であることは言うまでもありません。「ひと様のお役に立っている」という気持ちは、心に満足と張りをもたらし、その人を健康に保つことでしょう。手助けを求める高齢者に十分な救いの手を差し伸べられるように、手助けを行う側に回る高齢者をより増やす必要があります。
町の老人会に入っているか
男性27.7% 女性32.9%
地域で何かの役割を持っているか
男性19.0% 女性6.3%
地域でサークル活動や習い事、同好会に入っているか
男性15.2% 女性21.5%
いずれも地域社会への参加状況を尋ねています。高齢者が社会やグループに参加する方法として「老人会」が一番多く利用されます。同じ年代の人たちが集まり話しがしやすいという面があると思われます。
一方で「サークル活動や同好会」も老人会に次いで利用されており、趣味を同じくする者の集まりも居心地が良いものと思われます。
最も少ない「地域での役割」は、役職数が少ないということもありますが、それなりの責任が伴い、役割を担うことを尻込みされている面もあると思われます。
それよりも、もっと注目すべきことは7割の高齢者が「老人会」に入らず、8割の高齢者が「サークル活動や同好会」に入らず、9割の高齢者が「地域での役割」を持っていないということです。大部分の高齢者が、定期的な社会とつながりを持たずに暮らしていることは、高齢者が友人や家族、夫婦、自分自身といった狭い範囲のなかで日々の生活を送っているということでしょうか。
あるいは、社会とつながりたい気持ちは持っているが、参加したいと思えるようなグループが無い、ということなのでしょうか。もちろん、様々な生き方があるので「老人会」や「サークル活動や同好会」に入らず、「地域での役割」を持っていないことが、即、問題であるとは言えませんが、少なくとも高齢者のひきこもり現象は防ぐ必要があると考えられます。
高齢者にゆとりのある時間を豊かな気持ちで過ごしてもらえるよう、高齢者は何を望み、地域はそれに対してどう応えることができるのか。より一層、考えていく必要があると思われます。
地域でパソコン教室があれば参加しますか
男性29.2% 女性21.4%
学習意欲と地域社会への貢献意欲を尋ねています。「パソコン教室への参加意欲」は「サークル活動や同好会」の加入率とほぼ同じで2割です(四日市市が実施しました「IT講習」の受講者で高齢者が過半数を占めることを考えると、すこし少ない気がします)。自宅を出て、趣味や学習に参加しようとする高齢者が2割いるということです。
では、残りの8割の高齢者は趣味や学習意欲が無いのかというと、今はさまぎまなメディアがあることで、自宅でも趣味や学習に取組むことができます。そのため、この数字をもって高齢者の学習意欲がおもわしくない、とは言えないでしょう。ただ、高齢者の長い人生経験からにじみ出てくる知恵を、現在の地域社会で活かしていただくためにはパソコン等の情報入手、情報発信手段は重要です。パソコン教室等に参加して、新しい情報を入手していただくとともに、高齢者の知恵を情報発信していただきたいものです。
何歳になっても、新しいことに挑戦してみようという意欲を失わないよう、高齢者に対する動機づけや応援が地域として必要になってきます。
現在、どこかの病院に通っていますか
男性67.5% 女性70.0%
介護認定を受けていますか
男性10.0% 女性16.2%
約7割の高齢者が、からだに何らかの変調をきたして病院通いをし、1割の高齢者が自力での生活が困難になるほど心身機能が低下し介護認定を受けています。
老人会やサークル等には3割の高齢者しか参加していないのに、病院には7割もの高齢者が通っています。この割合が逆だったらと、思わずにはいられません。病院に通うのではなく、老人会やサークル等に通うことを目指し、高齢者の健康増進に向けて、高齢者個々人や地域での取組みが大変重要と考えられます。
また、介護認定を受けるまでに心身機能が低下した高齢者が1割いるわけですが、介護保険の制度や介護施設サービス事業者が充実してきたとはいっても、元気に暮らすのが一番で、介護保険は利用しないにこしたことはありません。健康増進(心身ともに)へ向けて、待ったなしの取組みが地域に求められています。
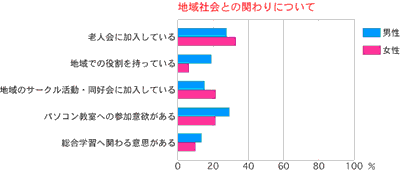
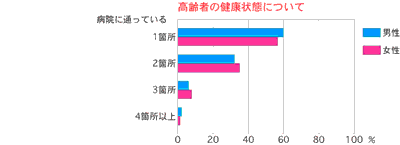
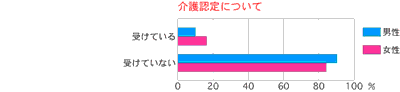
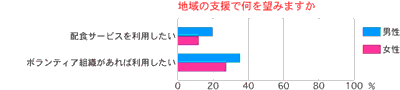
≪追記≫
高齢者と一口に言っても、60歳代と90歳代とでは30歳もの開きがあります。30歳もの年齢の開きがあれば、意識も行動も健康状態も大きく違うわけで、60歳代から90歳代までの高齢者のデータをひと括りにして分析し、活用するには無理が生じてしまいます。データの活用の仕方に工夫が必要となります。
高齢者の意識調査(意見、要望)の総括
高齢者の意識調査から意見、要望を集約して、その内容を整理してみますと実にさまざまな問題点が挙げられています。地区の老人会や自治会、社会福祉協議会、民生委員など各種団体や役割に対するニーズも数多く寄せられています。ここでは高齢者に関するものについて以下にまとめてみました。
1 地域の情報
2 地域の交通
3 趣味およびサークル活動
4 支援関係
5 防災の手助け
1 地域の情報については、高齢になればなるほど情報は狭い地域に限定されていきます。確かに多くの回覧や配布物など地域情報の資料が回ってきますが、隅から隅まで目を通すことは厄介なことです。必要な情報を取捨選択することも高齢者にとっては面倒なこ とです。
地区広報の紙面をみれば地域のニュース、催し物、趣味およびサークル活動、高齢者大学の学習会が一目でわかるなど、高齢者に特化した地域情報の提供が望まれています。
2 地域の交通については、高齢化と共に外出を公共交通機関に頼らなければならず、市街地に比べて交通の便の悪い当地域において、将来の交通の便が危惧されています。
なかには、将来を考えて当地域から市街地へ転居したいと言う住民もいますが、住み慣れた地域から引っ越しされる人の胸中を思うとき、残念でなりません。
この問題は当地域だけで解決できるものではなく、四日市市北部地域で広域的に検討し、取組み、解決していかなければならない問題と言えます。
3 趣味およびサークル活動については、交通の便(不便さ)、生涯の仲間づくりなどから考えて、地域における趣味の会、サークル活動に参加したいという要望があります。
ただ、仕事を持っている場合は地域に関わることが少なく、また、会社(仕事)一筋で生活してきた人にとっては、新しく地域のサークル活動に参加することは勇気のいることでしょう。
人は多くの他人と接することで喜びも楽しみも得られますので、サークル単独の紹介や勧誘ではなく、例えば、八郷のまちづくり委員会から地域全体への案内などが必要ではないでしょうか。また、高齢者の多くがパソコン教室の設置を望んでいます。
4 支援関係については、高齢化社会が進展するにつれ、ますます必要性の高まる課題だといえます。なかでも高齢者がふれあう場とか、ケアハウス、宅老所の設置が望まれていますし、八郷西地域においては地区市民センターが遠いこともあって、その出先機関の設置要望があります。
また、八郷地区の電話帳の更新についての要望が出ています。地域の電話帳は家族の名前が載っているのと、載っているのが地域の人に限定されているので高齢者にはとても使い易いということでしょう。
5 防災の手助けについては、最近、東海地震、南海地震、東南海地震の発生が想定されています。そのために地域における防災活動はもちろんですが、各家庭における防災対策も必要になります。たんすなど家具類の転倒防止の対策が早急に望まれます。
阪神大震災におきましても、家具の転倒で多くの人が負傷し、なかにはそれが原因で亡くなった人もいます。高齢者の方の多くが家具の転倒防止に対する手助けを求めています。早急に対応すべき課題だと思います。
仕事を持っていますか
仕事はフルタイムかパート勤務か
八郷地区の18歳から59歳の女性で仕事を持っている割合は、63.4%となっています。労働力調査年報(H11年)の15歳以上の女性の労働率は、49.6%となっていることから、当地区の女性は働きやすい環境が整っているものと思われる。
また、労働形態からみると、H13年の四日市市雇用実態調査報告書では、事業所に従事している女性労働者の雇用形態別構成比は、常用労働者(フルタイム)49.3% パートタイマー41.9%、派遣・出向労働者6.0%、臨時労働者2.8%という結果が出ています。八郷地区ではフルタイムの女性が47.2%となっており、市全体と同様の状況が伺えます。一方で女性の60%以上が仕事を持っておりながら、その内の半数以上がパートタイムについている、いわゆる女性がまだまだ補助的な仕事しか就くことができない社会の仕組みがあり、当地区においても同様の結果が出ているようです。
DV(ドメスティックバイオレンス)の言葉を知っているか
夫から命の危険を感じるほどの暴行を受けた経験のある妻が約20人に1人(4.6%=H11年総理府資料)いるなか、家庭内暴力や夫婦間暴力は民事不介入、法は家庭に入らずを理由に被害者の救済が必ずしも十分に行われてきませんでした。
このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るため、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護する法の整備がなされました。
意識調査の結果、八郷地区の女性の34%が「DVの言葉を知らない」と回答していますが、DVの言葉や意味を知ることの啓発を行う必要があると考えられます。
インターネットやe-mailを利用しているか
18歳から59歳の女性のなかで、インターネットやe-mailの利用者が52%を占める高率には正直なところ、びっくりしています。利用者の年代構成にもよるでしょうが、今やパソコンが情報の収集、発信の主役になってきていることを強く確信しました。今後の地域情報の収集や発信の方法を考えていくなかで、検討を要する大きな課題といえるでしょう。
隣近所とのお付き合い(会話)はあるか 80.8%
地域のサークルに加入しているか 12.5%
地域行事へ参加しているか 23.4%
地域で何か役割を持っているか 12.5%
ボランティア活動に参加しているか 8.4%
参加する気持ちはあるか 45.2%
いずれも地域社会への参加状況を尋ねています。女性が(地域)社会とのつながりを持つことは大切なことで、その状況についていくつかのことを問うています。
一番身近な隣近所とのお付き合いや会話はあるかの問いに、80.8%の方が「ある」と答えています。日々、顔を会わすことの多い間柄だけに当然の数値ではありますが、残りの約20%の方が主婦層なのか、独身者なのか気になるところです。
また、地域のサークルヘの加入や行事への参加となると、10%から20%の低率でたいへん寂しい参加状況といえます。四日市市がH12年に実施した「生涯学習についてのアンケート」結果では、継続的な学習(地域活動、サークル活動等)をしている方が42%ですから、今回の調査結果はかなりの低率といえます。
ボランティア活動への参加状況はそれよりも低率を示し、今後の地域活動の取組み方を工夫する必要があると考えられます。
日本はボランティア活動が育ちにくい土壌といわれていますが、この調査結果からみると当地区は仕事を持って、あるいは子育てで忙しい女性が多いなか、半数近くもの女性が「ボランティアヘの参加意志あり」の回答をしています。これはその方たちの地域への帰属意識が高まれば、また、条件整備がなされれば、地域貢献度アップの大きな要因となる訳です。ボランティア活動の予備軍が地域に十分いるということです。
今後の課題は、ボランティア予備軍の「最初の一歩」をどう引き出すかを工夫し、タイムリーに仕掛けることが必要となってきます。
地域での役割を持っているかの問いかけに、12.5%の方が「持っている」と答えています。役割というと自治会の役員をはじめ、諸団体の役員や民生委員などの役割を指していますが、男女共同参画社会基本法は男女が社会の対等な構成員として、民間団体においても、方針の立案および決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として行うとしています。
この際に、地域活動におきましても伝統やしきたりということで、男尊女卑や性別役割分業を温存していないかを点検することも大切なことと考えます。
子育ての不安や悩みを持ったことがあるか 68.1%
今、持っているか 34.0%
地域における子育て支援は必要か 80.7%
地域に子育て支援の場所や活動はあるか 29.3%
子育ての不安や悩みを持ったことがあるかの問いに、68.1%の女性が「ある」と答えています。今回の調査対象のなかに、子どものいない女性が含まれていることを考慮すると、子育て経験がある女性のほとんどが、不安や悩みを持ったことがあると考えられます。その結果として、80.7%の方が子育ての支援が必要と感じているのでしょう。ところが、それだけ多くの方が子育ての支援が必要と感じながら、当地域に支援の場所や活動はあるかの問いに対して、70.7%の方が「ない」と答えています。
核家族化が進んでいる今、子育て支援がほしい、助けて、と言う母親の声に、今、地域が真剣に耳を傾けて「何をどうすべきか」を考えることと、行動を起こす必要があるのではないでしょうか。
また、一方で、現在行われている「子育て支援事業」を地域の方に知っていただき、参加していただけるように広報活動にも力を注ぐ必要があります。せっかくの取組みも必要とする人たちが「知らない」ではもったいない気がします。
子育ての問題は、多くの女性のかつて苦労した道。今、苦労の真っ最中。これからが心配、不安。このような思いなのでしょう。
今後の社会の担い手としての子どもだけに、女性(母親)だけの問題とせず、広く地域の支援活動に、市民活動に展開していくことが大切ではないでしょうか。
子どもに注意することができるか 92.2%
子どもの行動は知っているか 90.1%
子どもと会話はあるか 86.8%
子どもと朝食を一緒に食べるか 62.2% 時々 24.3%
夕食を一緒に食べるか 82.2% 時々 12.6%
子どもの弁当は作るか 70.4% 時々 10.4%
子どもの学校行事には参加をするか 74.0% 時々 16.4%
授業参観には出掛けるか 78.6% 時々.11.3%
これらの問いに対する集計結果の意外な数値に驚いています。現在、四日市市の生涯学習課においては、乳幼児期、少年期を通して以下のような目標を掲げ、家庭教育の充実を図ることにより、子どもの健全育成に取り組んでいます。
乳幼児期における子育ての不安や悩みの問題、地域における子育て支援の問題。また、少年期には豊かな心情の育成や基本的な生活習慣の確立、健康な心身の基礎の確立、地域や家庭の教育力の向上と健全育成、地域活動における学習機会の確保と社会性に対する態度の育成などです。
子どもの幼児期、少年期の人格形成には家庭の教育が大きく影響します。子どもに全く無関心の家庭に対して、行政、地域の行動には限界があります。このデータを参考に行政にできること、地域でできること、各家庭でできることは何かを三位一体で考え、八郷のまちづくりに活用していきたいと考えます。
女性の意識調査(意見、要望)の総括
女性の意識調査の記述欄から意見、要望を集約して、浮かび上がった問題点をまとめてみました。
1 介護で困っていること
*在宅だと代りがなく、自由時間がなくなり、心身ともに疲れる。
*地域からの支援、手助けがない。
*施設の不足や施設が近くにない。
*結構お金がかさむ。
*実家の親を見ているケースが多い。
*介護の実態や介護保険、施設、用具、相談窓口などの情報不足。
2 地域に何か望むこと
*不法路上駐車があまりにも多い。
*中高生の自転車のマナーが悪い。
*犬の糞の後始末やマナーの悪さ。
*リサイクル含むゴミ問題。
*術路灯が暗い、もっと明るくして。
*防災体制の見直しと強化を。
*公共交通の便が悪い。
*家の近くでサークル活動が出来ないか。
*通学路の見直しと整備を。
*ボランティアについて知りたい、やりたい。
*近くに総合病院がほしい。
*行事が多い、減らして。⇔行事を増やして。
*近くに図書館がほしい。
*住民自ら考え行動し、自分たちの手でまちづくりを。
*交番の設置要望(多数)。
*人間関係の結び直し。
*パソコン教室開いて。
*地区、町の各種「まつり」の再興を。
3 必要な子育て支援の取組み
*学童保育所の設置に至急取り組んで欲しい。他の地区にはあるのに。
*児童館の設置を望む。他の地区にはあるのに。
*子どもを一時預ける場所が欲しい。病院、美容院、急な外出時に。
*病児保育。近くにないし、仕事を休みにくいし。
*子どもたちが安心して遊べる場所が欲しい。広い公園や遊具の整備、自然の中など。
*保育システムの見直し拡充を望む。年齢、時間、収入など制限が多い。
*中学生にも給食を。
*子どもたちにも祭や地区行事の思い出を残してやって。
*近くに気軽に立ち寄れる子育ての相談の場が欲しい。
*親子の交流の場や楽しい行事が欲しい。子と子、母と子、父と子、親と親、老人と子など。
*子育てが先か、仕事が先か、どちらも大事だが原点から考えてみては。
4 自由意見欄
*近所付き合いやふれあいの場が減ってしまった。
*親子共々しつけ教育が必要。子は両親を見て育つ。
*大人も子どもも挨拶運動を、子どもたちの集団登校での挨拶はうれしい。
*PTA、子供育成者会のあり方の見直し。
*今のところ学校週5日制の実りは少ない。
*仕事を持つ女性のための環境整備を望む。
*男女共同参画の趣旨を地域でも、家庭でも生かせ。
*子どもたちも、お年寄りも共に集える公園がない。または少ない。
*老人を元気にする老人の憩いの場、宅老所、シルバー喫茶など作って。
*地域の各種情報をネットで検索できるようにしてほしい。
以上、各記述欄からの発信要旨を列挙してみました。今回、2223名の方々からアンケートにご協力をいただき、慎重に集計、整理検討してきましたが、その63%を超える方々が何らかの形でお仕事を持っておられ、学童保育所の設置には強い関心と、要望を示されました。
厳しい経済情勢の狭間で、仕事と子育ての両立に悩み、ゆれる姿がひしひしと伝わってまいりました。
すべてのご要望に、今すぐ手掛けたい思いはありますが、地域でできること(地域のどの役割で担うのか)、行政にお願いや相談しなければならないことなど、整理をしながら着実に取組んでいく必要があると考えます。
地域主体、住民主体の時代といわれ、行政もはっきりとその方向性を打ち出している昨今、今までのように何もかも行政に依存する「おんぶに抱っこの」時代は終わったことを認識する良い機会かもしれません。
| 対象者の学年 | 男子(人) | 女子(人) | 合計(人) |
| 小学5年生 | 073 | 081 | 154 |
| 小学6年生 | 124 | 061 | 185 |
| (計) | 197 | 142 | 339 |
|
|
|||
| 中学1年生 | 182 | 175 | 0,357 |
| 中学2年生 | 176 | 173 | 0,349 |
| 中学3年生 | 197 | 171 | 0,368 |
| (計) | 555 | 519 | 1,074 |
赤字は質問事項です
塾(習い事)へ通っているか 中学生71% 小学生85%
何カ所通っているか
全国的にみて、三重県は通塾率が高く(H12年度全国推定調査で中学枚が1位、小学校高学年が3位である)、当地区においても同様の結果と思われる。また、当地区において、中学生よりも小学生高学年の子どもたちの方が通塾率が高いのは、塾のなかに ピアノ、ソロバン、習字などの習い事を含んでいるものと考えられます。
一時は、塾(習い事)に通っている子どもが多くて、遊ぶ子どもがいないという地域の声がありましたが、最近は世の中の様子が大きく変わり、「大学を出ても…」、「一流会社に就職しても…」生涯安心して生活できる保障がないという風潮から、塾に対する親や子どもの考え方も少し変化しているようです。しかしながら、通塾率が下がるとは思えません。
本年度から、学校週5日制が完全実施され、子どもたちが土・日曜日をどのように過ごすか、また、どのように過ごさせるかが課題になってきています。
塾通いについても多様な選択肢の一つではありますが、いくつもの塾通いや自宅学習に多大な時間を割かれ、家庭や地域とのつながりを持てなかったり、いろいろな活動の機会が奪われたりすることは如何なものでしょう。
朝食は食べますか
中学生 84% 時々 12%
小学生 88% 時々 10%
夕食は家族と一緒に食べますか
中学生 63% 時々 32%
小学生 55% 時々 42%
朝食は誰と食べているのか、また、どのような物を食べているのかはこの調査からはわかりません。実態として、「食べている」と言っても、パンだけとか、牛乳だけ飲んでくるとか、食事の時間も含めて問題点が考えられます。
全体から見る比率としてはわずか(小学生2%、中学生4%)ではありますが、朝食を食べない子どもがいます。食べないのか、朝食の用意がされないのかも気になるところです。同時に中学3年生の男子では「時々食べる」が20%を占め、驚いています。
夕食については、中学生にもなると塾やクラブ(部)活動の関係から、家族と一緒に食事をする回数は減少してきますが、小学生高学年の「時々食べる」と「食べない」との合わせた数値が45%もあり大きく気になるところです。
親との会話はありますか
中学生 76% 時々 22%
小学生 87% 時々 11%
主に(父、母)どちら
中学生(父親)19% (母親)81%
小学生(父親)27% (母親)73%
親(家)の手伝いはするか
中学生 24% 時々 59%
小学生 34% 時々 55%
親との会話の頻度や、とくに母親との会話が多いという点は納得できる結果といえます。小学校男子では、母親よりは少ないものの、父親と会話をする事が多くみられます。これは日々、地域における少年団活動や、子供会活動に父親が比較的参加していることで多くなっていると考えられます。また、中学生男子は女子に比べ、発達(反抗期)の関係で大人と話しをする機会が少なくなっていることもあるようです。
中学生の男子において、「家の手伝いをしない」子どもの数値が高いと思います。手伝いは習慣が大切だと考えられますが、小さいときから家族で役割分担をし、助け合うことにより、家族の絆を深めることにつながります。
地域の行事に参加したことはありますか 中学生 94% 小学生 98%
ボランティア活動に参加したことは 中学生 58% 小学生 57%
地域の行事にはほとんどの子どもが参加をしています。また、ボランティア活動においても、すでに地域と学校(子どもたち)が連携して取組んでいますが、地域の行事にしても、ボランティア活動にしても地域や学校や個人が単独で行うのではなく、それぞれ連携をして行うことにより、より大きな効果や成果をあげることができるのではないでしょうか。
行事やボランティア活動への参加の方法を今までのように、大人が全てのことを(企画から準備、当日の役割まで)御膳立てして、子どもたちはお客さまのような形で参加をすることから、子どもたち自らの発想で、企画、運営から実行までできるようなものになれば、これはたいへんすばらしいことです。
子どもたちに「任す」ということには地域の、或いは地域の大人の考え方や思いを転換させる必要はありますが、子どもたちが「育つ」ために大切なことではないでしょうか。
土曜日は何をして過ごしていますか
地域でほしいスポーツクラブ
土曜日は学校で培った能力を活かして、地域との関係を保ちつつ自己を見つめながら「自分探し」を行う機会であるといわれています。
調査結果は、中学生は男女ともクラブ(部)活動で、小学生においては男子が少年団(スポーツ)活動、女子が友と遊ぶが1位を占めました。続いては中学生の男女ともに友と遊ぶ、家でのんびりとするが上位を占めるなか、小学生の塾(習い事)通いの多さは気になるところです。
中学枚において、クラブ(部)活動は教育課程の一環として自主的、自発的な活動を展開したり、集団生活や社会生活のルールを身に付けさせたりするのに有効な手段であるといわれています。また、運動部の活動では体力の向上や健康の保持、増進などに重要であるとされています。
また、地域でほしいスポーツクラブの中で、学校のクラブ(部)活動にはない、いくつかのことを望んでいます。しかしながら、中学校におけるクラブ(部)活動は教員の数が限定されているなか、子どもたちの全ての要望に応えることが難しい状況も生じ、地域での総合型スポーツクラブの誕生がまちづくり、子どもの健全育成に欠かせない要件になりつつあるのでしょうか。
家庭でのんびりすることは大切なことではありますが、いつもだらだら、のんびりでは困ります。また、地域における少年団(スポーツ)活動が盛んなことはたいへん喜ばしいことではありますが、試合をするうえで勝つことにこだわり、その思いがあまりにも表面に出て子どもたちの関係がギクシャクしたり、月曜日に疲れがたまっていたりするようでは良くありません。指導者の心構えがより大切になってくると思われます.
学校は楽しいところですか 中学生 87% 小学生 85%
相談できる友はいますか 中学生 90% 小学生 88%
全般的に男子の否定的な数値が多いと思います。この二つの設問の回答数値がほぼ同じような傾向を示しているところから、「学校の楽しさ」と「相談できる友を持つ」ことは双方に影響を与え合う共通の要因があると考えられます。
また、この二つの設問が中学生におけるクラブ(部)活動への加入と、小学生における少年団(スポーツ)活動への参加の有無と少なからず関連がある、とみることはできないでしょうか。活動的でない子どもや、親の都合でクラブ(部)活動やスポーツクラブに参加できないことにより、友だち関係の形成が左右されるならば、それらの子どもたちに学校や地域は、どう関わっていくのかを考えることが大切といえるでしょう。
住んでいる地区の好きなところ、嫌いなところ
自然が好きという子どもたちがたいへん多くいます。市内でも自然が多く残っている数少ない地域です。自然が残っていることは素晴らしいことで、子どもたちがそれを今強く感じています。これからのさまぎまな活動のなかに「自然」を取り入れて実践していく必要を感じます。
また、ふれあいや祭が好きという子どもも多く、子どもたちが楽しめるような「まちづくり」が期待されているなかで、準備やかたずけの難儀さから、子どもの望む楽しみが一つ二つと消えていく町もあり、地域や大人社会の元気を取り戻してほしいと願わざるにはいられません。
一方で、多くの子どもがごみが多くて汚いことを嫌いと言っています。ごみ拾いや花づくりのボランティア活動はすでに行われていますが、地域全体で、大人も子どもも一緒になって行うことのできる「まちづくり」の取組みが、まちを美しくすることの第一歩ではないかと思います。
公園や広場があるから好きだ。他方で公園や広場がないから嫌いだ、と言っています。「もっともっと公園や広場がほしい」ということでしょう。地域のなかをもう一度、今までと違った視点で見つめる必要があるのではないでしょうか。
ぼくの夢、わたしの夢
子どもたちの多くは、将来の職業を「夢」として捉えています。男子は小中学生とも野球やサッカーのスポーツ選手になることを望み、一方で中学生は教師や保育士を、小学生は大工、漫画家、棋士などになることを夢見ています。女子は小学生で獣医・トリマー、ケーキ・パン屋、芸能人になることに憧れ、中学生は保母・保育士、獣医・トリマー、看護士を夢見ています。
子どもたちの「夢」は学年が上がるにつれて現実的なものに変化しています。学年とともに職業観を育てていくことが大切になってきます。
社会見学で地域の人々の働いている姿を見たり、総合的な学習の時間などに、働いている人の話しを聞いたり、実際に働くことを体験することなどが大切になってきます。
当然のことながら、このような取組みで職業に対する考えが徐々に変化することはわかっていますが、実践する学校において人材や、体験場所の確保が容易でないこともあり、地域として大いに協力をしなければならないところです。
子どもの意識調査の総括
子どもたちは誰によって育てられるのだろうか、また、子どもたちはどのような環境のなかで育っていきたいのだろうか、誰もが知っていながら、なかなか手を差し延べてくれないのが実情です。
子どもの居場所は基本的には家庭です。次いで地域を考えることになるわけです。
子どもにとって地域は友だちと遊ぶ場であり、家庭外の大人と接する場となります。地域の行事や、ボランティア活動に参加することによって、社会的存在感を認識することができるようになります。
また、年齢が進むにつれ、子どもたちは家庭の外に居場所を求めるようになり、その受け皿として、地域の環境づくりが大切になってきます。
家庭の教育力が、核家族化によって低下してきている今、子育ての実践に接する機会が少なくなり、また、体験による子育てのノウハウを受け継いでいないこともあり、やがて、そのことが子育てに関する認識不足として何らかの問題を生むことになります。そのために地域や行政が連携のなかで、新たな姿を構築していく必要があるといわれています。
隣近所との人間関係が、以前に比べ希薄になってきています。また、高齢化の進行もあって、地域という姿が薄れてきています。こんな時こそ地域の影響力について考えるべきであると思います。
地域は個々の家庭を支えるものであり、家庭では得られない情報の源です。地域は子どもの遊ぶ場所であり、子どもの成長を支援する場所だといえます。
大人同士の付き合いの煩わしさを理由に、自治会への加入や子供会への参加を敬遠する親が増加してきているなかで、地域の活動を通して大人たちがふれあい、ネットワー クを形成していくことで、地域の影響力を高めていくことが大切です。
地域の社会資源は、いつでも子どもが利用しやすい環境に整備されることが大切であり、また、そこで行われるプログラムは、子どもにとって魅力的なものでなければならないでしょう。自然や地域の歴史や産業、伝統行事などを大切にし、その学習資源と子どもたちとの直接のふれあいによって、子どもの生活の充実と活性化を図ることが必要と考えます。
そのために自然環境の保全、人材バンクの充実、リーダーの育成などが重要になってきます。また、多世代間交流による取組みも重要視されることになります。