|
|||||
| 八郷の いにしえ | |||||
| 八郷地区は、縄文時代中頃から朝明川の北側、朝日丘陵南縁の伊坂町周辺で集団生活が営まれ(西が広遺跡)、弥生中期頃になると丘陵地周辺の低湿地帯で農耕が行われていたと考えられています。最近の第二名神高速道路工事に伴う発掘調査で、県内有数の広さの伊坂城址(室町〜鎌倉時代・城主:春日部太郎左衛門尉と言われています)や菟上(うながみ)遺跡(弥生時代中期頃・大型の掘立て柱建物を含むかなり大きな集落跡と考えられている)、金塚(こがねづか)遺跡(弥生時代後期頃の環濠をめぐらせた高地性集落跡・住居跡や多くのお墓の跡、銅鐸の破片なども見つかっています)など城や村落跡、墓域をはじめ縄文時代から鎌倉時代くらいまでの沢山の出土品や井戸跡などの遺構とともに私達の祖先の暮らしぶりが少しずつ明らかになってきています。 | |||||
|
現在も伊坂ダム入り口の県埋蔵文化財センター整理所では、発掘された土器などの遺物の整理、分類、記録、保管などの地道な作業が続けられています。 |
|||||
| 大化の改新(645年)による律令国家の成立とともに、朝明郡の大金(おおがね)郷(萱生、平津、中村)と訓覇(くるべ)郷(山村、広永)に属していました。平安時代になると、伊勢神宮の荘園が各地に出来ていきましたが、当地区にも、内宮山村御厨(みくり)(山村)、内宮鶴沢御厨五十町(千代田)、能原御厨(萱生)、新能原神田(中村)、弘永御厨六十町(広永)が出来、寛仁元年(1017年)朝明郡は伊勢神宮領となりました。 | |||||
| 室町時代にはいると、北勢地方には土豪四十八家が割拠し、萱生城に春日部氏、広永城には横瀬氏が居城し、この地を支配しました。乱立抗争の繰り返される中で、三重郡千種城主常陸介忠治が萱生城を攻撃しましたが、城主の春日部俊家は堀をめぐらし、朝明川の水を引いて防戦に務めたため、城はついに落ちなかったと言います。しかし、この城も織田信長軍の伊勢進攻の際、兵糧攻めにあい、春日部俊家はあえなく降伏落城(永禄11年、1568年)したのでした。いまもその当時の遺構や悲話が残っているそうです。 | |||||
| 江戸時代(1603年・江戸開府)は初め桑名藩領で(1601年の慶長6年3月3日・家康四天王の一人本多忠勝、十五万石で桑名城入城、のち元和三年・1617年松平定勝入城)、文政6年(1823年)武州(武蔵の国)忍藩領、天保13年(1842年)幕府領となり、安政元年(1854年)再び忍藩領となりました。江戸時代中期の人口は、約1,700人、350戸と言う記録が残されています。 | |||||
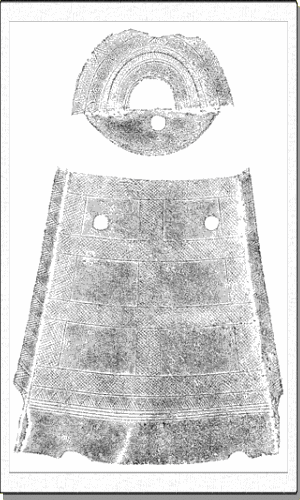 また文久2年(1862年)伊坂村の重地山で、弥生時代後期のものと推定される扁平紐式袈裟文銅鐸(へんぺいちゅうしきけさもんどうたく)が、たまたま薪拾いに来た地元の男達二人によって地中から発見されました。現在は通称伊坂の銅鐸と呼ばれ、市立博物館に展示されています。 また文久2年(1862年)伊坂村の重地山で、弥生時代後期のものと推定される扁平紐式袈裟文銅鐸(へんぺいちゅうしきけさもんどうたく)が、たまたま薪拾いに来た地元の男達二人によって地中から発見されました。現在は通称伊坂の銅鐸と呼ばれ、市立博物館に展示されています。
◎銅鐸とは |
|||||
明治4年、廃藩置県によって安濃津県に属し、翌明治5年三重県に所属、明治22年の町村制実施により、萱生、中村、平津、千代田、伊坂、山村、広永、広永新田(現山分)の八カ村を合併、八郷村となりました。おどろく事に当時の産物の項目には朝明川で捕れる鮎や、町内一帯の松林で採れる松茸などが書かれています。ともに環境が良くないと取れないものばかりです。『四日市公害』と言う言葉が忘れられかけていますが、自然はあるもののそれだけ環境が後退していると言う事なのでしょう。子供たちには今以上に美しい自然を残してあげたいものです。
|
|||||
| 昭和に入ると大恐慌に続いて第一次大戦、第二次大戦と、庶民にとっては大変苦難な次代が続き、戦前の小作農の人たちは大変苦しんだと言われています。 第二次大戦中、四日市市内は海軍の燃料廠(塩浜・現在の三菱化学のあたり)があった関係もあり大空襲に遭い焼け野原になりましたが、このあたりでも一部空襲を受け焼夷弾が落とされ民家が焼けたそうです。 |
|||||
| 昭和29年、三重郡八郷村から四日市市に合併、現在に至っていますが、昭和30年代までこのあたりはのどかな田園地帯で、春には近鉄富田駅あたりまで菜種の花で黄色一色に染まりました。当時は人家も少なく、旧東海道の松並木も遠望できたほどです。 | |||||
| また、この地区は昔から大変教育に熱心で、選挙の投票率なども高かったと言う記録が残っています。 | |||||
| 最近では旧八町に加え、昭和40年に北永台が、44年には平津団地、翌45年にはあかつき台団地がそれぞれ造成され、更に伊坂台団地も開発されて人口は急激に伸び、すでに団地の人口が旧八町を上回ってきています(67.8%)。現在は20の自治会に分かれており、42年前の昭和35年から見ても、人口が4.2倍に増えている事が分かります。 人口の推移は「八郷の今」→「人口」をご覧下さい |
|||||
| 更に詳しい八郷地区及び四日市市の歴史についてお知りになりたい方は、八郷地区市民センター図書室にて四日市市史全巻が閲覧できる他、中央緑地公園にある四日市市史資料倉庫にて膨大な資料を閲覧する事ができます。 | |||||
| また地元の篤志家により起された各町の昔語りや聞き書きがあるようですので、夫々の町の古老などにお尋ねになってはいかがでしょうか。 | |||||
|
最近発掘された遺跡に関する資料については、『あさけのいにしえ』と言う発掘に関する調査ニュースなども発行されていますので、詳しくは県埋蔵文化財センター(多気郡明和町・0596-52-1732)にお尋ねください。なおホームページアドレスは下記の通りです。アクセスしてみてください。
http://www.museum.pref.mie.jp/maibun/ |
|||||
| 四日市市教育委員会から『四日市市・遺跡マップ』が発行されています。(有料・一部300円) 地区市民センターか教育委員会へお尋ねください。 八郷地区の範囲はここをクリックしていただければご覧いただけます。
|
|||||
| その他、お知りになりたい事柄があれば『八郷まちづくり委員会』までお知らせください。ご要望の多いものから順次追加書き込みをして行きたいと思います。 | |||||
| 八郷人物往来 | |||||
|
(その壱) もともと萬古焼は、江戸時代の桑名の商人、沼波弄山(ぬなみろうざん)が、京焼きの尾形乾山の流れを汲んで、お隣の朝日町小向(おぶけ)(最近窯跡が発掘されました)に窯を築いて、赤絵を用いた茶道具を中心に焼き始めたのですが、彼の作品はいずれもたいへん見事で大人気となり、長く繁盛する事と自分の作品が永遠に誇り得る物としての自信を込めて、『萬古』または『萬古不易』と言う印を押したのが起源とされています。 |
|||||
