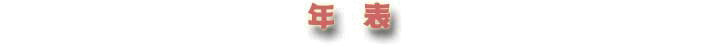
| 年代 | 西暦 | できごと |
| 縄文時代・中期 | B.C.2000 | 伊坂町で集団生活が営まれはじめる(西ヶ広遺跡) |
| 弥生時代・中期 | A.D.100 | 伊坂町周辺に大規模な集落が形成される(西ヶ広遺跡、菟上遺跡など) |
| 大化元年 | 645 | 律令国家の成立に伴い、朝明郡に属する |
| 寛仁元年 | 1017 | 朝明郡、神宮領となる |
| 永禄3年 | 1560 | 茂福の合戦に、萱生城主春日部氏出陣 |
| 永禄11年 | 1568 | 萱生城、伊坂城、織田信長軍に攻められ落城 |
| 寛永16年 | 1639 | 広永村の川村平左衛門、広永新田(現山分町)を開墾 |
| 文化13年 | 1816 | 山村の庄屋伊藤善八、十王山に横穴を開け、水道工事を完成(善八水道・一部現存) |
| 文久2年 | 1862 | 伊坂村の重地山で弥生時代後期のものと推定される扁平紐式袈裟文銅鐸、通称伊坂の銅鐸を発見する(現在市立博物館に展示されている) |
| 明治10年 | 1877 | 開明学校(後の八郷小学校)開校 |
| 明治22年 | 1889 | 萱生、中村、平津、千代田、伊坂、山村、広永、広永新田(山分)の八か村を合併、八郷村となる |
| 大正10年 | 1921 | 広永新田を山分と改称 |
| 昭和6年 | 1931 | 三岐鉄道、富田ー東藤原間開通、平津駅、萱生駅(後に暁学園前と改称)設置 |
| 昭和28年 | 1953 | 三岐鉄道、バス運行開始 |
| 昭和29年 | 1954 | 四日市市に合併 |
| 昭和39年 | 1964 | 金属工業団地(黄金町)ができる |
| 昭和40年 | 1965 | 暁学園 (中学、高校、短大) 富洲原から現在地に移転 |
| 昭和41年 | 1966 | 伊坂ダム(工業用水ダム)として完成 |
| 昭和43年 | 1968 | 平津新町の団地造成中にパラステゴドン象の臼歯の化石が発見される |
| 昭和44年 | 1969 | 東名阪国道の建設に伴い、伊坂町西ヶ広遺跡の第一次発掘調査始まる 平津団地造成 |
| 昭和45年 | 1970 | あかつき台団地造成始まる 朝明水源地設置 |
| 昭和47年 | 1972 | 八郷中央幼稚園設立 |
| 昭和49年 | 1974 | 平津町郷土資料館開館 |
| 昭和51年 | 1976 | 山村ダム完成 |
| 昭和53年 | 1978 | 八郷西小学校開校 八郷サイクリングコース完成 |
| 昭和55年 | 1980 | 中村町に東名阪自動車道の四日市東インターチェンジが出来る 富田・山城有料道路開通 |
| 昭和56年 | 1981 | 八郷地区市民センターを改築移転 |
| 昭和63年 | 1988 | 萱生町に四日市大学開校 |
| 平成4年 | 1992 | 八郷小学校100周年を祝う |
| 平成15年 | 2003 | 伊勢湾岸自動車道開通 |